 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
◆生涯の仕事となったこの連載 私は、この連載を引受けた時、10回か長くても1年間と考えていた。ところが今、既に4年目に入っている。書き始めてみれば、書いておきたいことが次から次へと出てきて、今や45回、もうすぐ50回になる。今では私にとって生涯の仕事になっていると感じている。次回何を書こうかとする思いよりも、今何を書いて置かなければ、とする思いの方が深くなっているのである。 ◆教程とは何か、そして教程はどう作られたらいいのかを問い直す その私の耳に噂が入ってきた。「平川さんが、新しいスキー教程作りに入り、スキージャーナル社と新しい教程の写真撮影を終えている。」というのである。
◆ 私は学校の教科書を作る仕事をしていた 私は若い頃、教科書会社に奉職して、少、中学校の教科書を作る仕事をしていた。その経験は私の生涯にとって貴重なものとなっている。
◆ オーストリアスキーの発展と進化に学ぶ
|
 1971年発刊された新オーストリア・スキー教程 表紙は前年のヴェーレンテクニックの分解写真 |
◆1955年教程が内在していた2つの大きな過ちの指摘
1970年オーストリアは、ヴェーレン・テクニックと呼ぶ沈み込み技法を発表、1971年には新しいスキー教程を発刊した。そのオーストリアスキー教程は福岡孝行さんの名訳で日本語版(実業の日本社発行)が作られたが、日本のスキー界はその新教程にも何の反応も見せていない。
福岡孝行さんは、その翻訳本の最後にオーストリアスキーの大きな変化に触れて、長文のレポートを書いている。そこには、1955年教程が内在していた2つの大きな過ちを指摘し、それがどのように解消され、どの様な新提案がなされているかについて解説している。しかし大熊さん達はそうした事実を完全に無視したのである。当時日本のスキー界の頂点にあった大熊勝朗さんの過ちは大きい。
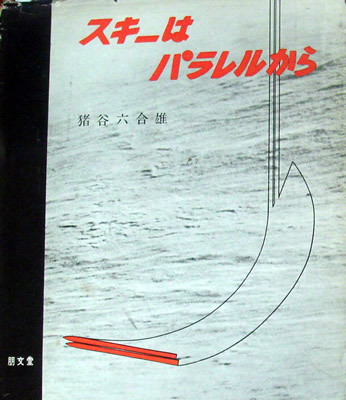 ”スキーはパラレルから” 猪谷六合雄 この本が1958年の暮に発表されたことにただ驚くしかない。 「シュテムシュブングはどこまで習熟してもパラレルにはならない。 パラレル・クリスチャニアは初めからパラレルに導入される 指導法によれば容易に身につけることができる。」 その主張は、見事という言葉以外に送る言葉は見当たらない。 1955年に発表された、旧オーストリア教程は、 スキーのバイブルとまで呼ばれ世界中に普及していたが、 そのバイブルにあえて挑戦した論文であった。 |
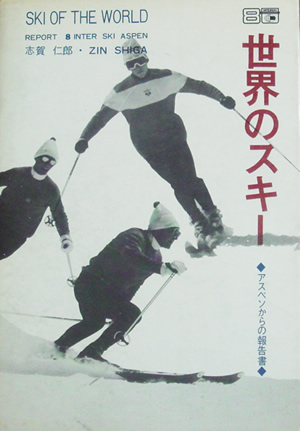 『世界のスキー』 |
◆「スキーはパラレルから」「世界のスキー」の2つのレポート
当時日本のスキー界には、猪谷千春選手の父親猪谷六合雄さんが、オーストリアスキーの過ちを指摘して、「スキーはパラレルから」と題する著書を発表している。何と1958年のことなのである。そして1968年のアスペンにおけるオーストリアスキーの大転換に関して私のレポート「世界のスキー」が発売されたのだが、その2つのレポートはオーストリアスキーの総本山サン・クリストフで世界のスキーの法王と呼ばれたステファン・クルッケンハウザー教授に絶賛され、世界各国の指導者に届けられた。というのに日本だけその2つのレポートを無視したのである。
何故か!! 私は今になってようやくその謎に気がついたのだが、猪谷六合雄さんの論文には大熊さんにとって自分の父親である六合雄さんへの反発があったと思われるし、私のレポートに対しては、「何だこの若僧は」といった強い反発の意識があったのだろうと思う。
日本のスキーは10年20年の後れをとることになった。
◆日本のスキーヤー達がどれ程、新しい技法に憧れていたか
1970年、オーストリアはサン・クリストフに世界中のスキー指導者を集めてヴェーレン・テクニックを発表した。その発表は日本にもなじみ深い、ミッシェル・フルトナー(フランツの息子)、バルトル・ノイマイヤー、フランツ・ラウター、ルッギー・シャラーといった人々が立ち合っている。その日から世界中のスキー国で沈み込み技法への研究が始まった。だが、日本ではそれより早い1968年から、熊の湯のパンチョこと佐藤勝俊君の深雪の技法、悪雪の技法が研究されていたのである。
パンチョターンの研究は、全く新しいターンの技法として日本のスキー界の中に浸透していった。
サン・クリストフでのヴェーレン・テクニックの発表に立ち会った私が平沢文雄に送った手紙は、日本の沈み込み技法の研究を一気に加速させることになった。
その春、私はヨーロッパのワールドカップ取材を終えて帰国し、すぐに浦佐を訪れた。そこで私は驚くべきシーンを目撃した。浦佐の斜面にサン・クリストフのブンデスハイム横に造られた段々畠と同様の斜面が作られ、その斜面に浦佐の精鋭たちが挑戦していたのである。平川仁彦、関健太郎をはじめとした浦佐の誇る名スキーヤーたちが、ヴェーレン・テクニックの習得に没頭していたのである。
その後私は浦佐からすぐにデモンストレーター選考会の行われる八方尾根を訪れた。そこには、浦佐で見た光景よりも更に驚くべき状況を見た。八方のコブの斜面でデモンストレーター選考会に出場するであろう名手たちが沈み込みのターンを練習していたのである。日本のスキーヤー達がどれ程、新しい技法に憧れていたのかが判る。
※連載46話につづく
[08.06.01付 上田英之]]


