【日本のスキーを語る 連載11 志賀仁郎(Shiga Zin)】
スキー教師とは何か
※連載11は、独立となります。

ホテル アンゲラルアルム シルベスタ(大晦日)には着物で 志賀さんとご夫人 |
◆ヨーロッパではスキー教師に案内されて昼食をとる

志賀さんが今年の正月を過ごした
オーストリアのホッホグーグルスキー場 |

アンゲラルアルムホテル |

ホッホグーグルスキー場 |
 |
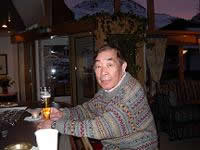 |
 |
 |

ドイツの友人と |
 |

イタリアの山々 |
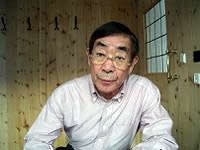 |
 |
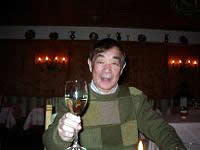 |

リフト中間点でテント ビールが飲める |
 |

イタリアとの国境と壊れたピステン |
 |

インスブルック空港 18人乗りプロペラ |
ひる12時を過ぎると私の泊まっているホテルのレストランは、あっと言う間に一杯になる。そのほとんどがスキー教師に案内されてやって来るスキーヤー達である。5人、6人のグループ、スキー教師と2人だけで入ってくるご老人、とお客はさまざまだが。
スキーウエアーを入り口近くのハンガーにかけ、手袋、帽子などは、その下の棚に置いて、テーブルにつく。スキー場のホテルで一番忙しいのがこの時間である。
子供たちだけのグループは、別の部屋で食事をとる。大人の世界を邪魔しない配慮であり、子供用の食事(キンダーメニュー)のサービスがやりやすい工夫なのである。
◆スキー教師はそのスキー場の案内人
どのテーブルもすごくにぎやかで、ドイツ語、英語、フランス語が飛び交っている。その話にちょっと耳を傾けてみると、スキーの話をしているのは、ほんのわずか、いわゆる世間ばなしなのである。老人は自分の孫の自慢話、若いグループは、夏に行った南の島の話など、ちょっと日本とは違うなと思う。
こうした場面では日本ならスキー技術の関する話が多いのではなかろうか。1時になると一斉にお勘定となって、みんな出て行く。その風景が面白い。スキー教師は何もせず、彼に習っている生徒が支払うのを見ているのである。子供たちのグループも親からもらってきた自分の食事代を払い、スキー教師の分をみんなで分割して払っている。
その時刻が終わらないと私たちそのホテルの客は食卓を見つけることはできない。そうした風景は、コースの途中にあるヒュッテ、レストランでも同じこと。ヨーロッパのスキー場の極めて当たり前の光景なのである。
ベテランのスキー教師の中には、その日の昼の食卓をリザーブして、何人かの客を連れてやってくる。こうした昼食の仕方を見るとスキー教師の仕事は、そのスキー場の案内人ということが判る。スキー教師は受け持ったスキーヤーの技術レベル、体力に合わせて快適な、そのお客に合ったコースを選び、お客のふところ具合を勘案して入るレストランを決めメニューを説明している。
日本では、教える側と教わる側に先生と生徒という関係が当たり前。もっぱら習う側の生徒が先生にサービスするという光景がみられるのである。
◆古い友人同士が一緒にスキーを楽しんでいる様な
コースに目を移してみよう。スキー教師は、スキー場のどこに居ても良くわかる。そのスキー場の名を入れたそのスキー場の教師であることが一目で判るユニフォームを着ているからである。
2人3人、多くて5人程度の生徒たちを連れて、滑っている。その滑りは、習う側の技術を正確につかんでいるのだろう。無理のないスピード、無理のないターン弧を見ていても安心できる滑りなのである。
今日の天候ならこのコースがこの人たちに快適なはず、何時頃どのリフトが空いているかといった事を知りつくした教師の誘導でいつの間にかスキーがうまくなっている。というのがヨーロッパ流なのである。
スキー教師と生徒との会話では、トーマス、ハインツといったファーストネームでのやりとりで、雰囲気は古い友人同士が一緒にスキーを楽しんでいるといった風景なのである。
◆教わる生徒を番号で呼ばない
私は日本のスキー場に居るチャンスが少なく、ここ10年ほど日本のスキー指導の現場を知らないのだが、その10年ほど前に見た光景を思い出す。10人程度の生徒を受け持った教師は、生徒を胸につけたゼッケンと呼ぶ番号札の数字で呼び、一列に並べて、「はい何番さん滑って」とやっている。ひとり、ひとりに丁寧に「方の向きがちょっと少ないね」、「膝をもっと曲げてー」と注意の声が聞かれる。スキー講習会と呼ばれる場は、どこも同じようなものだった。3キロ4キロと長いコースを持つ八方尾根ですらコースの途中で停まって講習を受けるのが当たり前だったと思う。
教わる生徒を番号で呼ばない(ゼッケンを使わない)教習をはじめたのは、1960年のデリブルの講習会が初めてと記憶するが、オーストリアから帰国して開校された杉山進のスキー学校も生徒を何々さんはいどーぞと名前を呼んでいた。
◆ホッホグーグルの料金表を見てみよう
「ハンス、ちょっとここから急になるから気を付けて」、「あぁ判ったスピードを落として入るよ」と言った会話が交わされるのが聞こえる。日本の風景とは全く違うのである。
「それじゃ、僕らのもらう謝礼金と彼らが受け取る金じゃーぜんぜん違うんでしょう」と言った声が聞こえてくる。されスキー客がスキー教師に払う(スキー学校に払う)料金を紹介しよう。
ここホッホグーグルの料金表から見てみよう。教師を指名しないでスキー学校の窓口で申し込むと、1日(午前中2時間、午後2時間)52€(ユーロ)(7280円)、2日で98€(1万3720円)、一週間だと175€(2万4500円)かなりな金額になる。それが教師を指名するプライベートレッスンとなると、1日195€(2万7300円)、一週間になれば1日が166€となって6日間では996€で、日本円なら13万9440円。気の遠くなるような金額なのである。
地元のスキー教師に聞いてみると、若い新米のスキー教師で3万円から7万円、年をいってベテランの人気教師なら10万から15万ぐらいは稼ぐだろうと語った。
◆きびしい職業教育を2年間受ける必要がある
スキー教師は冬のいい職業といっていい。しかし、そのいい職業につくためには、いくつもきびしい関門がある。先ず、第一にきびしい職業教育を2年間受ける必要がある。「俺はスキーがうまいんだぞ」と言ったところで例外は認められない。あの英雄トニー・ザイラーやカール・シュランツですらスキー教師養成コースをサンクリストフのブンデスハイムで受講しているのである。
次に自分の地元のスキー学校に登録しなければ勝手に「俺はスキー教師の資格を持っているんだぞ」と人にスキーは教えることができない。
ここのスキー教師の大半が地元のホテルの息子や娘、地元の商店の親父だったりするのは、そういった条件を満たし、村の人々の同意を持ってこの職業についているからなのである。
私の泊まっているアンゲラルアルムという超高級ホテルのオーナーは、ギディ・アッカホルナーという超有名なスキー教師だが、その前歴は、オーストリアナショナルチームの女子のヘッドコーチであった。
その息子のアルミンは、少年時代からオーストリアチームのアルペン選手として活躍、選手をやめてスキー教師の資格をとり、今はオーストリアジュニアチームのコーチとして活躍している。
こうした素晴らしい経歴を持つ二人だがギティは、ホテルオーナーとしての仕事が忙しくスキー教師として働くことはなく、アルミンはジュニアチームのコーチの仕事で手いっぱい、ここではスキー教師として登録していない。
私たちの様なホテルの客は、時にはギディやアルミンと一緒に滑りたいと希望することがある。そうした要望にギディは、「スキーサファリ」と名付けたホテル客だけのグループでスキー場のコースをまわるサービスをやってくれる。それは全く無償なのである。1€でもお客にもらったら、それは重大な違反となるからで、ホテルのお客さんと一緒にスキーを楽しんだということになるのである。
こうしたオーストリアの職業として確立された状況は、私の知る、スイス、フランス、イタリアでもほぼ同じで、アメリカ、カナダ、そして新しいスキー文化を構築中のオーストラリアでも同じだと言えるだろう。
◆日本には特別な事情があるに違いない
スキーというスポーツが日本に入って既に100年を超えて、スキー文化における先進国といえる日本だが、スキー教師というのは、どんな職業なのだろうか。
日本では全日本スキー連盟が認定した指導員・準指導員がスキー教師となれる資格といえるのだが、それを取得する道はヨーロッパとは全く異なっている。
そこには何か特別な事情があるに違いない。私は、何年か前、雑誌に日本のスキー教師の特異な点を書いたことがある。
まず日本のスポーツ界の特異なところはスポーツの原点が、剣道、柔道、弓道という古くからの道といった考え方、それはスポーツでなくても、お花、お茶、という生活の中にある文化がほとんど習い事となり、何段とか何級、といった位がついて来るという日本にある社会常識が、近代スポーツであるスキーにも深く影響を与えていると思っている。
◆技術の高さを誇示する勲章が指導員
スキーを始めた人は、直ちにスキーの魅力にとりつかれ、一生スキーを楽しむようになる。スキー学校に入り、講習会にも参加するうちにスキーにはバッチ検定があり自分の技術がどのレベルなのかを知ることができるということが判る。それは剣道、柔道を習うと級や段が与えられるのと同じことだと思われる。
都会の若者たちでも「俺、今年1級をとるんだ」「何だお前まだ1級かよ、俺は去年準指導員とったんだぞ」「へえーすげー」なんて言う会話がごく普通に聞かれるのである。
雪に全く縁のない都会暮らしの若者たちがスキーにのめりこめば、どうしても自分の力量を示してくれる勲章が欲しくなる。
そのいちばん高い評価が指導員のバッジを胸にかざることなのである。指導員という資格が、それぞれその人の技術の高さを誇示する勲章である限り、雪に縁のない都会の若者たちが、やっきになるのも判る。東京都、神奈川県に北海道につぐ指導員の数があると言うのも判るのである。
そうした誇らしげな勲章をつけた指導員がヨーロッパのプロのスキー教師の様な職業意識を持った教師になれるだろうか。
◆山の名前や、生えている木の名前を聞かれたら答えられますか
私は昨年秋、神奈川県の指導員の集会に行った事がある。その時何人かの若い指導員に聞いてみた。「どこで教えているの」「はい、○○○スキー学校で働いています」と元気な声が返ってきた。そこで「スキー場の後ろにある山の名前や、生えている木の名前を聞かれたら答えられますか?」と重ねてたずねた。すると、「わかるわけないですよ、そんなことは地元の年寄りの指導員に聞いてくれと言うのです」と明るく答えた。スキーが人より一寸うまいばかりにつける冬の快適なアルバイト、生徒はみんな、僕と同じようにうまくターンができウェーデルンができる様に技術を習いに来ているんだ。
と考えている。うまい奴が下手な奴にスキー技術を教える。何も山の名前を教えたり、うまいメシ屋に連れて行ったりのサービスは必要ない。というのが、都会から行っているスキー教師たちの常識だろう。
近代スポーツも、古くからある日本のスポーツ文化の中で、ヨーロッパとは違う発達をしたと考えられる。スポーツだけではない、生活の中にとけ込んでいる。お茶やお花といった文化も、先生について習う、お稽古事となっているのと同じであろう。
また、日本のスキーだけが、ヨーロッパから見れば極めて古い、約50年前の指導理論を持ち、それを何度も改訂をくり返しながら、基本的な考え方を全く変えていないと言う、奇妙な現象、そして、バッチテストと呼ばれる選別作業が、古い教程の技術構成によって計られているということが、日本のスキーが100年を超えるという長い歴史を持ちながら、進歩を止めてしまっている不思議に突き当たるのだが、さて、日本のスキーは、今ヨーロッパで起きている技術革新をどうとらえ、どう消化し、新しい時代に合った波を生み出せるのだろうか。
◆スキー教師とはどんな職業なのでしょうか
かって私は、オーストリアスキーの総本山サン・クリストフでステファン・クルッケンハウザー教授に、極めて、初歩的な質問をぶっつけた事がある。「スキーとはどんなスポーツなのですか」「スキー教師とはどんな職業なのでしょうか」の二つであった。
やさしい顔で微笑んで教授はこう答えてくれた。「スキーとは自然との対話である」簡単だが極めて深い哲学であった。そして「スキー教師とは、その自然との対話のチャンスを都会の人々にも与えられる案内人なのだ」どちらの言葉も、今なほ深く私の心に刻み込まれている。そして教授は言葉をついで、「スキー教師は自然との対話に中で、その人が生きる喜び生きる勇気を与えられるかも知れない職業なのだ」 何と素晴らしい仕事ではないか。
スキー教師は、スキーの技術を教える職人の領域にしかいない。日本の現状を教授は2度の来日、そして数多くの日本の指導者たちとの接触の中でをどう見ていたのであろうか。
[2005年01月23日付 教育広報委員会 上田英之] |







