【日本のスキーを語る 連載37 志賀仁郎(Shiga Zin)】
インタースキーとは何だろう(その2)

横浜ランドマークタワーの前にて |
◆第12回セストのインタースキー 引き締めムードであったが…
1983年、イタリアの田舎町セストで第12回インタースキーが開かれた。ワールドカップのプレスルームで多くのイタリアのジャーナリストに「セストってどこ」と聞いたが、皆首をかしげて知らないと答えた。
スキーを専門としているスキージャーナリストさえ知らないセストは、ドロミテ山群の中の小さな村であった。私は、ドビヤッコの駅の近くの踏切で画用紙一枚にマジックペンで書かれていた案内板をみつけて、村に辿り着いた。
陽気な気質のイタリアでの行事とはとても思われない開会式であった。村のメインストリートを各国の代表団が行進する時も、デモバーンでの開会式場にも一切音がなかったのである。イタリアの人々は村の若者の結婚式でも田舎のサッカー試合でも、必ず楽隊が先導し、どんな小さな行事にも音楽がある。それが全くない行事を私はイタリアで初めて経験したのである。フィンク教授の蔵王への反撥を感じていた。
地味に進行されたセストだが、夜のムードは変えることはできなかった。各国の宿舎となった小さなホテルのバーはスキー教師たちの社交の場となっていた。インタースキーは各国のスキー教師たちの親善交流、情報交換の場となっていたのである。
このセストでは、日本は過大ともいえる期待を背負って参加していた。しかしその負わされていた期待は完全に裏切られた。レクチャー会場での発表では、「何を言いたいのかサッパリ判らない」と嘲笑され、デモバーンでの技術指導の演技では、さらに強い反撥を呼んだのである。この日を境に日本のスキーは世界から見離されてしまったのである。セスト以降、スキー国の誰も日本には目を向けなくなった。親密な関係にあったオーストリアでさえ、日本を見限ってしまったのである。日本スキー界にとって極めて不幸な出来事だったといえるだろう。
セストから次のカナダ、バンフの13回、そしてオーストリア、サンアントンの第14回は、セストの引き締めムードは薄れ、蔵王の友好ムードの風が流れていた時代といえるだろう。スキー教師たちの友好親善の集まりという空気は、もう引き戻すことは出来ないものになった。それと同時に「インタースキーとは何だ」という疑問が生まれ、大きくなっていた。

パンチョターン写真をホームページ用に選んでいただいています |
◆第14回サンアントン テーマ「スキーイスポ」
1991年オーストリアのサンアントンで第14回インタースキーが開かれることになっていた。その開催前の数年間に私は、そのインタースキーを取り仕切るフランツ・ホッピッヒラー教授を何度かたずね、サンアントンインタースキーをどんなテーマでどう進行させるかを話し合った。その当時、世界中で環境問題が語られるようになった時期であった。私たちは「スキー環境のインタースキー」にしようという結論に達していた。
しかし、それから数ヶ月たったある日、教授は「ZIN、あのプランは提案できないよ。環境問題を採り上げたら、スキーは環境を破壊するスポーツだからやめてしまえ、とする声が必ず上がってくるだろう」と力なく語った。
その当時(1988年〜1990年)ヨーロッパでは不幸な事故が数多く報道されていた。「スキー場の拡張、改造が大きな災害を引き起こす」とする報道であった。
サンアントンからわずか30分で行けるエッツタールが豪雨に見舞われ、深い谷のあちこちに山崩れ、がけ崩れが起き、谷の中の村々が水に埋もれ泥にまみれた。エッツからオーバーグルグルに行く道路も寸断されてほとんど交通不能となった。この大災害は、谷の奥の氷河の上のスキー場の開発が引き起こした人災だと報道されたのである。
ホッピッヒラー教授は環境問題をあきらめて、1991年インタースキーのテーマを「スキーイスポ」とすることになった。
I’SPOとは、毎年春ドイツミュンヘンで開かれるスポーツ用品見本市の略である。「商業主義と共存できるスキーを語り合おう」という意味だった。

サンアントンインタースキー日本選手団の入場 |
◆オーストリアは村を挙げ、国の威信をかけてこの大会を開催したのである
サンアントンインタースキー(1991年)は華やいだムードで進行した。大規模なブラスバンドの先導で町のメインストリートを各国の国旗を先頭とする19ヶ国の代表団が行進した。
蔵王インタースキーに逆戻りした様なインタースキーとなった。ホッピッヒラー教授が意図した「商業主義との共存」というテーマは薄れてしまっていた。ミュンヘンのI’SPOに全力投球した各スキー用品メーカーは、サンアントンに余力を残していなかったのだろう。ロシニョール、サロモンのわずか2つのメーカーがデモンストレーション会場の下にサービステントを設けただけだったのである。
サンアントンインタースキーは、蔵王インタースキーを上回るともいえる華やかさで進行した。それは、インタースキーを発案した国、インタースキーを牽引してきた国と自負している国として、「あの蔵王に負けないインタースキーを」といった願いであったろう。
そして同時にサンアントンは多くのお祭り行事を持っていた。ハンネス・シュナイダーの生誕100年、スキークラブ創立90周年、サンアントンスキー学校の70周年、さらにより重要な行事としてインタースキーの40周年を記念する行事として、このサンアントンインタースキーが企画されていたのである。
サンアントン、オーストリアは村を挙げ、国の威信をかけてこの大会を開催したのである。多くの人が集まり、この村は蔵王大会を上回るといえる程の大きなお祭りの舞台となった。

サンアントンインタースキー 日本のデモンストレーション |
◆日本のデモは美しいフォーム、流麗な流れを演じて大観衆から賞賛を浴びた
午前中に行われる参加各国の技術デモンストレーションは、第一日目の地元オーストリア、そしてアルゼンチンのデモで開始されたが、どの国のデモも多くの観衆を集め、拍手に迎えられた。しかし、そのデモは全ての国がほぼ同じ技法を展開していた。「世界のスキーをひとつに」とする1968年第8回アスペン大会に提唱された夢は、スキー技術の面では実現していたのである。
サンアントンで注目されたのはノルディックスキーのデモンストレーションが追加され、スノーボード、障害者のスキーの指導法が公開されたことであろう。インタースキーは雪の上で行われるあらゆるスポーツの可能性について話し合う場となった。レクチャー(講演)には12ヶ国が参加、さまざまな報告、そして将来への夢が語られた。
日本は「機能的スキーを求めて」という表題で日本におけるスキースポーツの発展の課程、そして「現在の日本のスキー」が語られ、日本人はスポーツの中に美を見出したと報告した。日本人の精神文化に触れる福岡孝純さんの講演は、各国の参加者に「高邁な話であった」とする好評、そして「日本人が型にこだわり、美にこだわる謎がとけた」とする評価があった一面「何をいっているのか判らない」とする声もあったのである。
このサンアントンインタースキーに参加した日本人は、史上最大の2500人を超えて最大となった。SAJのデモンストレーターは、斉木隆、渡辺一樹、金子裕之、大平成年、佐藤譲、吉田幸一、我満嘉治、佐藤正人、沢田敦、竹村幸則の10名であった。
日本のデモはこのサンアントンでも古いオーストリア技法を展開して各国を驚かせたが、美しいフォーム、流麗な流れを演じて大観衆から賞賛を浴びた。
うまいと見た人、美しいと感じた人、そしてなつかしいと感じた人さまざまであったろう。専門家の間では、「日本は初参加以来25年もたっているのに、そしてオーストリアと極めて近い関係にあるのに、世界のスキーの進歩になぜ気がつかないのか」とする声。「インタースキーの主要国のひとつといえる国なのに何故インタースキーの流れを無視するのか」といった声が聞こえていたのである。
このサンアントンで、メインストリートに面したホテルのテラスで、はちまきを締め、法被を着た日本人グループが勇壮に太鼓を打ち鳴らし、日本酒の樽をあけ、通る人に日本酒をふるまっていた。野沢温泉インタースキーNOZAWAへの招致活動だったのである。そのふるまい酒が効果があったのかどうか、次回第15回インタースキーは野沢に決定した。
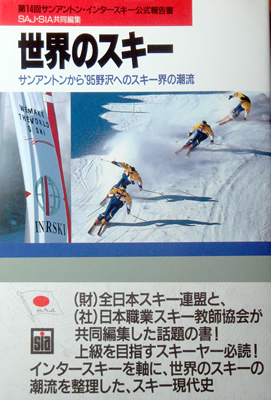
1991年サンアントン第14回インタースキーの報告書として、
私が中心となって、SAJ,SIAが共同編集したレポート。
内容のほとんどは、私が書いたもの。
「サンアントンから’95野沢へのスキー界の潮流」とあるが、
”インタースキーとは何”への回答と思えるのだが。
この本が出た後も日本では、「インタースキーって何」
のままなのである。(山と渓谷社) |
◆インタースキーを振り返る(7回〜9回)
ここでサンアントンまでの14回のインタースキーの辿って来た道を振り返ってみたい。私が直接見て来たのは1968年アスペンの第8回大会以降だけれど、1965年第7回大会の記録から、そこで起きたことは推測できた。
激しい技術論争を繰り広げて来たオーストリアとフランスが歩み寄り、もうこれ以上の対立はしないといった姿勢を見せたのである。注目されたのはオーストリアが発表した、やや短めのスキーを使い両スキーを開いたままに操作する、ブライトシュブングと呼ばれた指導法であった。
1968年、アメリカアスペンで開催された第8回インタースキーはオーストリア、フランスの歩み寄りがはっきりし、私はこのアスペンインタースキーを ”合意のインタースキー”と呼び、インタースキーが掲げてきた「世界のスキーをひとつに」という理想が実現した。このアスペンで注目されたのはドイツの提出したウムシュタイク・シュブングの技法であろう。両スキーを交互に蹴ってターンをつなげる技法は、圧倒的な迫力を生んで各国の代表たちをうならせた。
1971年ドイツのガルミッシュ・パルテンキルヘンで開かれた第9回インタースキーは、新技法の展示会となった。オーストリアはその前年サンクリストフの斜面に造られた段々畑のような斜面で、フランスの理論家、ジョルジュ・ジュベールの提唱する「アバルマン技法」(飲み込む技法)に近い動き、フォームを採るヴェーレンテクニック(波の技法)を発表し、その技法をガルミッシュで披露したのである。
その沈み込み技法は、ドイツ、スイス、フランスをはじめ世界各国が発表した。スイスのカール・ガンマは「世界中のスキー国が同じ技法にそれぞれ別の名前をつけて発表したインタースキー」と批判したのである。
日本はそのインタースキーに、熊の湯のパンチョ、佐藤勝俊君の技術を分析したとする曲進技法を発表している。
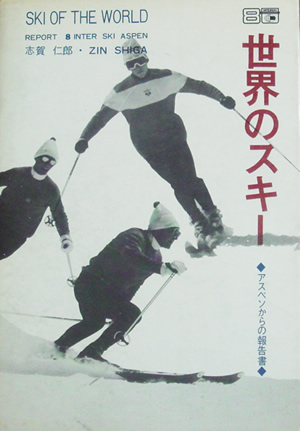
アスペン・インタースキーのレポートとして私が作った
”世界のスキー” 1968年(冬樹社)
この本はインタースキーの報告書として世界でたった一冊作られたもの
日本ではSAJの幹部の「アスペンではオーストラリアスキーは
一言一句も変わることはなかった。志賀の本は日本のスキー界を
混乱させる」として廃刊を強要された。
ステファン・クルッケンハウザー教授に絶賛され、コピーがとられ
世界各地のスキー教師養成コースの教科書となった。
ク教授は、私に会った時、「この本の表紙を見た瞬間にお前が
どうゆう動機で作ったかが判ったよ。」と語った。
表紙の写真はアスペンのデモバーンを滑るオーストリアのデモ(右上)
とフランスのデモである。オーストリアの新しい指導法から
生まれるパラレルシュブングだが、このフォームはかっての
フランススキーにあった技術が見え、フランスの2人のスキーは
強い逆ひねり前外傾が採用されている。
私に本の中でアスペンの合意とした姿が見えている。 |
◆インタースキーを振り返る(10回〜11回)
次の1975年、チェコのビソケタトリで開かれた第10回インタースキーは、新しい技法の発表も、目につく論文もなく極めて平穏な会議となった。参加者の関心はソビエト連邦の共産主義から解放されたチェコでスキーがどう行われていたのかといった点にあった。
そして1979年、東洋で初めて開かれるインタースキーが蔵王で開催された。(その詳細は、既に前回に書いているので省略する) 蔵王でインタースキーは世界中のスキー教師が集まるお祭りになってしまった。特記すれば、この蔵王大会から一般のスキーファンを対象に各国のスキー教師が指導するスケジュールが追加されたことだろう。
その蔵王インタースキーの後、スイスのカール・ガンマは、インタースキーの将来について次の様に語っている。「今後この会議を続けて行くには、会議の規模を縮小し、開催地の財政負担を軽減する方策を考えなければならないだろう。具体的にはデモンストレーションは2つに分け、ショウ的な部分は、「規定」と「自由」とに分け、技術的な発表は、あらかじめ決められたテーマに絞っての発表と自由な主張に分けて行えるようにすれば良い」というものであった。
巨大化するこの会議にブレーキをかけ修整しようとする提案であった。しかし、その提案は完全に無視されて、サンアントンインタースキーは蔵王と並ぶお祭りとなった。街中のホテルのバーや村の居酒屋は連日連夜、世界中のスキー教師たちの友好親善の場となり、各国のスキー教師の雇用条件の情報交換の場となったのである。
◆インタースキーの流れを整理してみよう
1995年第15回インタースキーは日本の野沢温泉で開催された。日本のスキーの故郷と自負する野沢は、村を上げてこのインタースキーを進行させた。参加国は35ヶ国、インタースキー史上最大規模の大会となった。
書いている事が行ったり来たりで読者は戸惑っているに違いない。申し訳なく思っています。そこで、ここに箇条書きでインタースキーの流れを整理してみよう。
1、草創期 1951年ツールス オーストリアのバインシュピール技法とフランスのパラレル技法の比較の大会
1953年ダボスでの第2回、1955年ヴァルディゼールの第3回、1957年のストーリエンの第4回、続く1959年ザコパーネの第5回と、オーストリアとフランスの対立は続く。この間にオーストリアスキー教程が発行されて、第6回(1962年)モンテボンドーネ大会では世界のスキー技法の流れはオーストリアに傾く。そしてオーストリアとフランスの両国の間にお互いの技術を尊重し、お互いに情報を交換しようとするムードが生まれた。
2、発展期から ”世界のスキーはひとつ”とする夢が語られる時代へ
1965年バドガスタインの第7回オーストリア教程への評価が高まり、バインシュピール技法が世界中に広まることになる。日本の初参加が認められ、日本は世界に向けて窓を開いた。
技術比較の論争は消えていた。
この時代、インタースキーは大会ごとに盛大となり、各国の技術演技も充実し、各国から多くの論文が提出された。
1968年アスペンの第8回は論争の時代から和解の時代へと移り、会場は和やかなムードにつつまれた。私はこのアスペンを「アスペンの合意」と呼んだ。
オーストリアは突然1955年の教程を廃棄して新しいオーストリア教程を発表した。それは古い段階的指導から、グルンドシュブングを習得すればあらゆる技法はその延長上にあるとするもの。まさに革命的な進歩であった。
このアスペンでのオーストリアの大転換を日本のスキー界は完全に無視して、そのアスペン以後も古いオーストリア技法を踏襲する数少ない国となった
3、技術革新の時代
1971年ガルミッシュ大会は、世界中のコブの斜面に対応する技術が発表されて、沈み込み技法への関心が高まった時代。オーストリアのヴェーレンテクニック、フランスのアバルマン技法、スイスのOKテクニック、そして日本もパンチョターンから発想された曲進技法を発表した。
大会の最終日、それらの技法を比較する「ターフェルピステ」と呼ばれる凸凹の斜面で、各国のデモンストレーター達による試演会が行われ、日本のデモチームの滑りに極めて高い評価が与えられた。
しかし、ビソケタトリ1975年大会では、日本は再び古いオーストリア技法を演じて、世界を驚かせた。
4、インタースキーは巨大なお祭りとなった
1979年、東洋で初めてインタースキーは日本の蔵王で開催された。参加国は24ヶ国、世界中でスキーが出来る国の全てが集まった。そして全ての国の技術が紹介され、多くの論文が提出された。インタースキーは巨大な規模の大会となった。
スキー教師たちは3年前に会った顔を見付け出し、お互いの今を報告しあった。そこにはインタースキーの目標として掲げて来た「世界のスキーを知り、世界に自国のスキーを見てもらう」とする目的は薄まり、「世界のスキー人を知り、それぞれの国のスキー事情を語り合う」といった友好親善の場となっていた。
情報伝達の高速化、その技術によって昨日サンクリストフで発表された技術は、次の日にはシャモニーに伝えられ、今日オーストリアが新しい論文を発表すれば次に日には世界中にその主張が伝えられる時代となっていた。
私のもとにも「昨日ウィーン大学の教授がこんな論文を発表して話題になっているぞ」といった情報がFAXや電話で伝えられる時代になっていたのである。わざわざ遠い国でのインタースキーに参加しなくても、全てのスキーに関する情報は直ちに届けられる。
「友好親善の楽しい集会」となったインタースキーが、年々参加国を増やし、また年々その領域を拡大して、雪の上で行われる全てのテーマが語られる時代となって、インタースキーは提出されたそれぞれのテーマが薄れてしまったと思われる。蔵王以降に「インタースキーって何?」とする声が聞かれるようになった。
今のインタースキーは草創期の目標を見つめ直し、新たなインタースキーを模索しなければならない時代に入っているのである。

野沢温泉インタースキーの開会式(インタースキー全記録) |
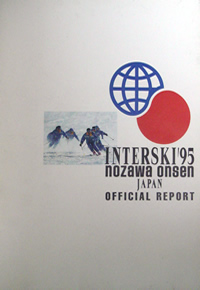
野沢温泉インタースキー 公式レポート
|
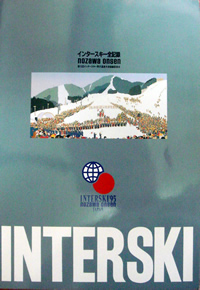 野沢温泉インタースキー全記録 野沢温泉インタースキー全記録 |
以上
[2007.10.25付 上田英之] |












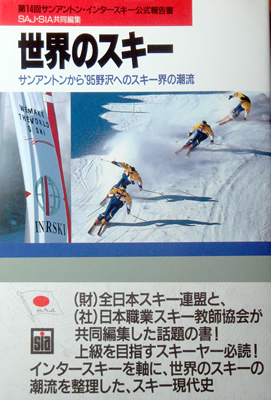
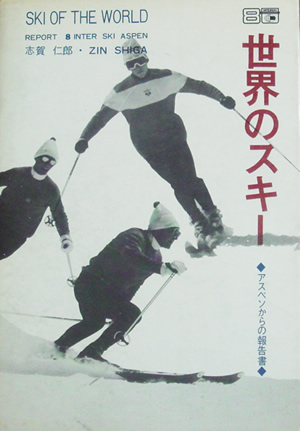

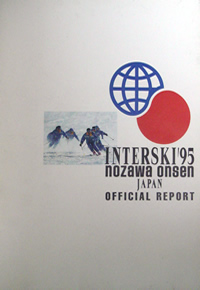
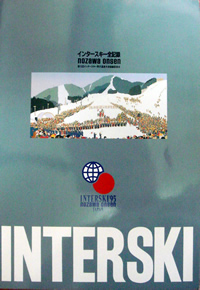 野沢温泉インタースキー全記録
野沢温泉インタースキー全記録